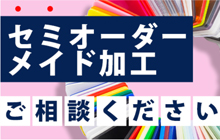目次
ポリエチレンとポリプロピレンはどう違う?まずは基本から理解しよう

私たちの生活や産業に欠かせない「プラスチック素材」は多くありますが、中でも特に注目されているのが「ポリエチレン(PE)」と「ポリプロピレン(PP)」という2つの合成樹脂です。
どちらも「原油」から作られる樹脂素材で、軽くて扱いやすいという共通点を持っています。
しかし、実際には耐熱温度や強度、透明性、用途などに明確な違いがあり、目的によって最適な素材を選ぶことが求められます。
この記事では、まずポリエチレンとポリプロピレンそれぞれの素材について詳しく確認しながら、違いの本質をひも解いていきます。
用途に合った素材を選ぶことで、製品の品質やコストパフォーマンスにも大きく影響しますので、しっかりと基礎から理解していきましょう。
そもそもポリエチレンとはどのような素材なのか?
ポリエチレン(PE)とは、エチレンを重合して作られる高分子素材であり、日用品から産業用まで幅広く活用されています。
その特性としては、「軽い」「耐薬品性が高い」「絶縁性がある」といった点が挙げられます。
また、加工性にも優れているため、大量生産に向いており、コストパフォーマンスが非常に良いという点も大きなメリットです。
ポリエチレンには「低密度ポリエチレン(LDPE)」「高密度ポリエチレン(HDPE)」「超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)」などの種類があり、それぞれ特性や用途が異なります。
例えば、LDPEは柔らかくラップフィルムやポリ袋に用いられ、HDPEは強度が高く灯油タンクやバケツなどに活用されます。
さらに、ポリエチレンは水に強く、冷凍環境でも性質が保たれるため、食品の包装材としても非常に適しています。
一方で、熱にはあまり強くなく、70〜90℃を超える環境では変形や溶融のリスクがある点には注意が必要です。
ポリプロピレンとは何か?使用される場面の特徴もチェック
ポリプロピレン(PP)とは、プロピレンを原料として作られる合成樹脂で、ポリエチレンと並ぶ代表的なプラスチック素材です。
最大の特徴は「高い耐熱性」と「優れた剛性・強度」にあり、熱湯を使う場面でも変形しにくく、耐衝撃性にも優れています。
また、無色透明に近く、見た目にも清潔感があり衛生的な印象を与えるため、食品容器や医療用器具にも多用されています。
ポリプロピレンは「ホモポリマー」「ランダムポリマー」「ブロックコポリマー」など、構造の違いによって種類が分かれています。
ホモポリマーは剛性に優れ、ランダムポリマーは透明性が高く、ブロックコポリマーは耐衝撃性と耐寒性が強化されています。
また、ポリエチレンに比べて紫外線に弱い点や、成形時に高精度が求められるなど、素材としての扱い方にコツが必要な面もあります。
とはいえ、ポリプロピレンは非常に軽量で、リサイクル性にも優れており、地球環境にも配慮された素材として多くの現場で選ばれています。
ポリエチレンとポリプロピレンの【共通点と相違点】をわかりやすく解説

ポリエチレン(PE)とポリプロピレン(PP)は、いずれも私たちの暮らしや産業に欠かせない重要なプラスチック素材です。
名前こそ似ていますが、それぞれに特徴があり、使用される場面や条件に応じて最適な素材が選ばれています。
ここでは、ポリエチレンとポリプロピレンの「共通点」と「相違点」を具体的に解説し、両者を正しく理解・活用するための知識を整理していきましょう。
まずは、両者にどのような共通点があるのかを確認したうえで、それぞれの違いを丁寧に掘り下げていきます。
素材の選定に悩んでいる方や、産業用途で使い分けたい方にとっても役立つ内容となっています。
両者に共通する特徴とは?実はたくさんある意外な共通点
ポリエチレンとポリプロピレンには、見た目や用途が似ているだけでなく、基本的な性質にも多くの共通点があります。
この2つのプラスチック素材は、どちらも「炭素と水素のみで構成されるポリオレフィン系樹脂」であり、燃焼時に有毒ガスを発生しないという特徴を持っています。
また、どちらの素材も比重が1.0未満と軽量耐水性・耐湿性に優れている点も共通しています。
成形性の高さも注目すべき共通点です。
ポリエチレンもポリプロピレンも、射出成形・ブロー成形・押出成形・真空成形など、さまざまな加工方法に対応できます。
さらに、両者ともに無味無臭で毒性がなく、安全性が高い素材として、食品用容器や医療器具などの用途にも利用されています。
以下の表は、ポリエチレンとポリプロピレンに共通する主な性質をまとめたものです。
| 共通の性質 | 詳細内容 |
|---|---|
| 構成元素 | 炭素と水素のみ(ポリオレフィン系) |
| 比重 | 約0.90〜0.95(非常に軽量) |
| 耐水性・耐湿性 | 吸水率0.01%以下で、水に強い |
| 加工性 | 射出・押出・ブローなど幅広い加工に対応 |
| 安全性 | 無臭・無毒で、食品・医療用途にも対応可能 |
このように、ポリエチレンとポリプロピレンは多くの点で共通していますが、使い分けには細かな性質の違いを理解することが大切です。
次のセクションでは、両素材の性能差や見た目、加工性の違いについて詳しく見ていきましょう。
ここが違う!ポリエチレンとポリプロピレンの代表的な違い
ポリエチレンとポリプロピレンは、どちらも軽量で加工性が高いプラスチック素材として広く利用されていますが、それぞれに異なる性質があるため用途に応じた使い分けが重要です。
まず注目すべきは、耐熱性と柔軟性の違いです。ポリエチレンは柔らかく低温環境に強いのに対し、ポリプロピレンは比較的硬く、高温下でも安定しています。
また、透明性や耐候性といった外観や環境への強さにも差が見られ、使用する場面によって大きく適性が変わってきます。
ここからは、具体的なポイントに分けて、それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。
耐熱温度と柔軟性の違いを比較してみよう
ポリエチレン(PE)とポリプロピレン(PP)は、似たような外見を持ちつつも耐熱温度と柔軟性において大きな差があります。
ポリエチレンは種類によって異なりますが、おおむね70〜110℃までの熱に耐えることが可能です。一方で、ポリプロピレンはさらに高く、100〜140℃の高温でも変形しにくいという特性を持っています。
柔軟性においては、ポリエチレンの方が圧倒的に優れており、袋状の包装材や曲げ加工が必要な製品に最適です。対してポリプロピレンは剛性が高く、形をしっかり保つ容器や部品類に適しています。
透明性・耐候性などの見た目と性能の違いにも注目
見た目に関しても、ポリエチレンとポリプロピレンでは異なる特徴があります。ポリエチレンは半透明の乳白色で、視認性はやや低いですが柔らかくやさしい印象があります。
一方のポリプロピレンは無色透明に近く、よりクリアな見た目が求められる包装材などに適しています。中身の確認が必要な容器やボトルに多く採用されている理由の一つです。
また、耐候性に注目すると、ポリエチレンは紫外線に対して比較的強く、屋外使用にも向いているという長所があります。これに対してポリプロピレンは紫外線やオゾンによる劣化が起きやすく、長時間屋外にさらす用途には向いていません。
【表で比較】主な物性の違いをわかりやすく整理
| 項目 | ポリエチレン(PE) | ポリプロピレン(PP) |
|---|---|---|
| 耐熱温度 | 約70〜110℃ | 約100〜140℃ |
| 柔軟性 | 高い(柔らかい) | 低い(硬め) |
| 透明性 | 乳白色で半透明 | 無色透明に近い |
| 耐候性 | 比較的高い(紫外線に強い) | 低い(劣化しやすい) |
| 加工性 | 高い(袋・フィルム等に適する) | 高い(硬質製品に適する) |
| 主な用途 | ポリ袋・食品包装・緩衝材など | 保存容器・医療器具・家電部品など |
このように、ポリエチレンとポリプロピレンは、見た目や熱への強さ、柔軟性において明確な違いがあります。製品の使用環境や目的に合わせて、最適な素材を選ぶことが大切です。
ポリエチレンの種類とそれぞれの特徴をおさえよう

ポリエチレンには複数の種類が存在しており、それぞれの特徴を理解することで使用目的に合った素材選びが可能になります。
特に注目すべきは、密度の違いによって分類される「低密度ポリエチレン(LDPE)」「高密度ポリエチレン(HDPE)」「超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)」の3種類です。
この章では、これら3つのポリエチレン素材について具体的な特徴や用途の違いを詳しくご紹介していきます。
素材の性質を正しく理解すれば、製品開発や材料選定において無駄なく効率的な判断ができるようになるでしょう。
柔らかくて加工しやすい「低密度ポリエチレン(LDPE)」とは?
低密度ポリエチレン(LDPE)は、名前のとおり密度が低く、柔らかさとしなやかさが特徴のプラスチック素材です。
非常に加工性に優れているため、包装材や柔軟な容器など、さまざまな分野で幅広く利用されています。
特に日用品では、ラップフィルムやポリ袋、チューブ容器などに使われることが多く、身近な素材として知られています。
LDPEはおおよそ70〜90℃の耐熱性を持ち、低温環境でも割れにくいことから、冷蔵・冷凍食品の包装にも適しています。
また、電気絶縁性や耐薬品性も高いため、工業用の部品や電線被覆材としての利用例も見られます。
下記のような用途での使用が代表的です。
- 食品用ラップや保存容器
- 洗剤などのチューブ容器
- 医療用輸液バッグ
- 緩衝材(プチプチ)やホース類
LDPEは軽く柔軟で安全性も高いため、さまざまな製品に対応できる素材ですが、一方で耐熱性や強度はそれほど高くないという注意点もあります。
そのため、使用環境に応じた選定が重要となります。
強度と耐熱性に優れる「高密度ポリエチレン(HDPE)」とは?
高密度ポリエチレン(HDPE)は、LDPEと比較して分子の結びつきが強く、より硬くて強度の高い素材です。
この素材の大きな特徴は、耐熱性・耐衝撃性・耐薬品性に優れているという点にあります。
そのため、レジ袋・灯油タンク・バケツ・コンテナなど、強度が求められる用途で多く活用されています。
HDPEは約90〜110℃までの耐熱性能を持ち、過酷な環境でも形状を保つことが可能です。
また、比重が0.94以上であることから、密度が高く剛性に富んでおり、硬いプラスチック容器の材料としても最適です。
透明性はやや劣りますが、その分、耐久性や耐候性に優れているのが大きなメリットです。
- 灯油タンク・ポリバケツ
- 薬品の保存容器
- 洗面器やレジ袋
- 文房具・建築資材・梱包容器
HDPEは、強度と耐熱性を両立したバランスの良い素材として、家庭用から産業用まで多くの分野で活用されています。
ただし、柔軟性には乏しいため、衝撃吸収性や曲げ加工が必要な場面では適さないこともあります。
極めて高性能な「超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)」もある
超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)は、名前のとおり非常に分子量が大きいポリエチレン素材であり、他の種類に比べて突出した性能を持つ高機能素材です。
分子量は100万を超え、優れた耐摩耗性・耐衝撃性・耐薬品性を兼ね備えているのが大きな特徴です。
UHMW-PEは、極端な環境下でもその性能を失わず、-200℃のような超低温環境でも性質が安定しています。
また、自己潤滑性もあるため、摺動部品や機械の可動部分にも最適です。
さらに、生体適合性があるため、医療分野においては人工関節や人工骨などのインプラント素材としても使われています。
- 産業機械や重機の部品
- 登山ロープや船舶用ロープ
- 人工関節・整形外科用インプラント
- 食品工場での搬送用ガイド
UHMW-PEは、非常に高価な素材ではありますが、他では代替できない性能を発揮するため、特別な機能が求められる現場で重宝されています。
その反面、加工には高度な技術を要するため、取り扱いの際は専門知識が必要になります。
ポリプロピレンにも種類がある!特徴の違いと用途を紹介

ポリプロピレン(PP)は、私たちの生活や産業に欠かせないプラスチック素材のひとつです。
この素材は高い耐熱性や軽さ、そしてコストパフォーマンスの良さで広く知られています。
しかし、実は「ポリプロピレン」とひと口にいっても、いくつかの種類に分かれており、それぞれの特徴や用途には明確な違いがあります。
この記事では、ポリプロピレンの代表的な3つの種類である「ホモポリマーPP」「ランダムポリマーPP」「ブロックコポリマーPP」について詳しく解説していきます。
どの種類を選ぶかによって製品の性能や用途が大きく変わるため、しっかりと理解しておくことが重要です。
素材選びで失敗しないためにも、ポリプロピレンの種類ごとの特徴と適した使用場面をチェックしていきましょう。
基本となる「ホモポリマーPP」の特徴と適した使い道
ホモポリマーPPは、ポリプロピレンの中でも最も基本的なタイプであり、プロピレン単体を重合して作られます。
その最大の特長は高い剛性と耐熱性にあり、常温から120℃近くまでの加熱環境でも形状を維持することが可能です。
この特性により、ホモポリマーPPは食品容器・電気部品・生活雑貨など、熱に強くて強度が求められる製品に多く使われています。
特に電子レンジ対応の容器や、繰り返し加熱するキッチン用品などには最適な素材です。
また、耐薬品性にも優れており、洗剤ボトルや医薬品関連のパッケージにも利用されています。
ただし、透明性や耐寒性にはやや劣るため、用途によっては他のPPタイプとの使い分けが必要です。
透明性・柔軟性が魅力の「ランダムポリマーPP」
ランダムポリマーPPは、プロピレンに少量のエチレンを共重合させて作られたタイプで、ホモポリマーと比較すると柔軟性と透明性に優れた素材です。
この特性により、視認性が重視される透明ボトルやパッケージ製品に数多く使用されています。
さらに、低温環境でも割れにくく、柔らかさが残るため、寒冷地で使う製品や冷蔵保存が必要な容器にも向いています。
実際には、クリーニング袋・透明折箱・家庭用収納ボックスなど、見た目や使いやすさが求められる日用品によく使われています。
一方、ホモポリマーほどの剛性や耐熱性は期待できません。
したがって、耐久性よりも柔軟さや美観を重視したい場合に適した素材だと言えるでしょう。
衝撃や寒さに強い「ブロックコポリマーPP」もチェック
ブロックコポリマーPPは、ホモポリマーPPをベースにゴム成分を加えて強化された特殊なポリプロピレンです。
この構造により耐衝撃性・耐寒性・柔軟性が大幅にアップし、過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。
主に使用されるのは、自動車部品・家電の筐体・建設資材など、強度や衝撃吸収性が求められるシーンです。
また、冷凍食品用のトレーや屋外用の容器など、耐寒性が必要な場面にも非常に適しています。
加えて、ブロックコポリマーPPは射出成形や押出成形など加工性の良さも持ち合わせているため、生産面でも扱いやすい素材です。
耐久性と柔軟性を両立させたい場合には、このタイプを選択することで製品寿命の向上やトラブルの低減が期待できます。
まとめ
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
ポリエチレンとポリプロピレンの違いについて深く知っていただけたなら幸いです。
アクリルデポではポリプロピレン板の販売をしております。お探しのお客様は以下のバナーよりアクセスください!